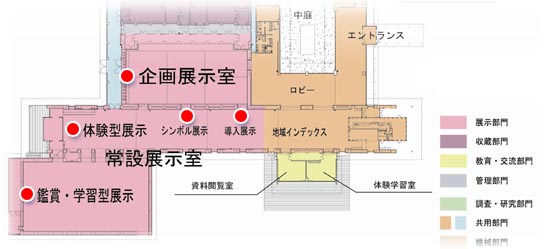|
|
|
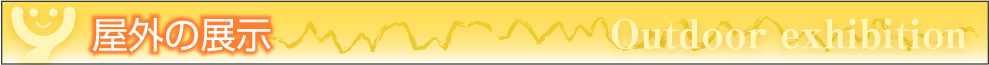 |

|
| |
| |
|
|
 山梨は大昔「海」だった!? 身延町小原島大露頭の化石 山梨は大昔「海」だった!? 身延町小原島大露頭の化石 |
| |
|
 |
|
今から約700万年前の山梨には、ふたつの大きな海峡的な海が広がっていました。ひとつは、現在の桂川(相模川)沿いの「古桂川海峡」。もうひとつは、富士川沿いの「古富士川海峡」です。
当館のメインゲートの脇に展示されている砂岩の塊は、当時の富士川海峡に堆積したものです。この海峡には、クジラやサメ、イワシなどの魚類が泳ぎ回り、海岸近くには、貝やウニなどの数多くの海の生物が住んでいました。
この砂岩のかたまりには、タマキガイ・フスマガイ・スダレガイ・フミガイ・ビノスガイなどの化石が含まれています。これらの化石は、身延町小原島で発見されたとても貴重な化石です。 |
|
| |
|
| |
|
|
 富士川水運の栄枯を見つめた鰍沢河岸の松 富士川水運の栄枯を見つめた鰍沢河岸の松 |
| |
|
|
|
総合教育センターとの間、当館駐車場付近に植えられている松は、富士川水運で栄えた鰍沢河岸に植えられていた松です。品種は三河黒松、樹齢は100年を越すものと思われます。害虫にやられ、多くの葉を落としましたが、現在でも青々と山梨の地を見つめています。
常設展示 「川を彩る高瀬舟」へ |
|
| |
|
| |
|
|
 余白の台座 余白の台座 |
| |
|
 |
|
メインエントランスに入ったお客様の目に最初に飛び込んでくるのは、中庭(光庭)に展示されている「余白の台座」です。
「余白の台座」は関根伸夫氏の作品で、中央には白御影石が配され、周囲には甲州の各地域から産出された岩石が配置されています。
周囲の岩石の内訳は、青石(南都留郡道志村)、クロボク(南都留郡鳴沢村)、甲州鞍馬石(甲州市大和町)、塩山玉石(甲州市塩山神金)、乾徳石(山梨市三富)、大沢石(鳴沢村)からなります。 |
|
| |
|
| |
|
|
 シンボルツリー ヤマナシの木 シンボルツリー ヤマナシの木 |
| |
|
 |
|
敷地北側のつどいの広場で、ひときわ大きく聳え立っているのがシンボルツリー・ヤマナシの木です。春には、左のような、白い可憐な花を咲かせます。
山梨県立博物館には、約4万本の山梨ゆかりの樹木が植えられています。季節ごとに色とりどりの花を咲かせ、果実を実らせます。開館前に定植してから、徐々に草花も育ってきており、これから更に成長していき、私たちを楽しませてくれることでしょう。 |
|
| |
|
| |
|
|
 道祖神 道祖神 |
| |
|
 |
|
敷地西側にある道祖神は、甲府市上石田自治会が所有していたものを、縁あって平成18年に当館におまつりしたものです。このような丸石を御神体とする道祖神は、甲府盆地やその周縁部に多く見られる形で、山梨県の道祖神の特徴でもあります。
道祖神は、集落に悪いものが入らないように守る神さまで、多くは道の交わるところや集落の境界にまつられます。それにならい、博物館でも建物を囲む道と敷地の外に通じる道とが交わるところにまつりました。また、山梨で道祖神祭りが行われる1月や7月には、博物館の道祖神も注連縄を張り替えてささやかなお祭りをしています。 展示室からは、アルプスと市街地そして桃畑と、山梨らしい景観を背にした道祖神を見ることができます。 |
|
| |
|
| |
|
|
 かいじあむの畠・もも畑・ぶどう畑 かいじあむの畠・もも畑・ぶどう畑 |
| |
|
 |
|
敷地西側の道祖神ちかくに、「かいじあむの畠」、「もも畑」「ぶどう畑」の3つの畑があります。
「もも畑」「ぶどう畑」には、甲州ゆかりの桃や葡萄の品種が栽培されています。「かいじあむの畠」には、郷土野菜や綿など、季節ごとに様々な作物が栽培されています。秋には、「かいじあむ収穫祭」など、収穫物をお楽しみいただくこともできます。 |
|
| |
|
| |
|
| |
 屋外のキャプション 屋外のキャプション |
| |
|
.jpg) |
|
敷地内の樹木には、左のようなキャプションによる説明が付されています。天気の良い日には、博物館のお庭のお散歩もおすすめです。
月に1度、「ボランティアによるお庭の見所ガイド」を開催しておりますので、そちらもご利用ください。
「ボランティアによるお庭の見どころガイド」 へ |
|
| |
|