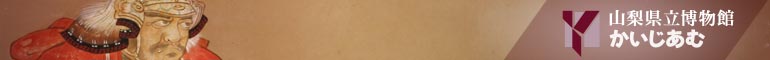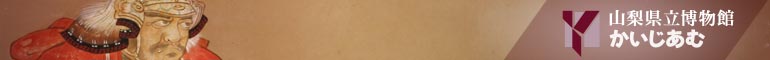平成18年11月7日(火)
午後6時から7時30分 |
県立美術館 白石和己 館長
「伝統の美を極める―人間国宝の作品」
※終了しました。 |
文化の重要性がいろいろなところで言われており、また文化の大きな要素として、伝統文化の再認識が言及されています。
そうした伝統文化の象徴のひとつが人間国宝といえます。人間国宝の制度ができてから半世紀がたちましたが、この制度がなぜ生まれたのか、どういう経過で成立したのか、またその意味や変遷について考えていきます。そして、ここでは人間国宝の工芸に限ってその作品についても魅力を探ってみたいと思います。 |
平成18年11月14日(火)
午後6時から7時30分 |
県立文学館 近藤信行 館長
「『青年』と『三四郎』」
※終了しました。 |
| 森鴎外の「青年」は、夏目漱石の「三四郎」に遅れること2年ほどして書き始められました。Y県から上京した作家志望の小泉純一の視点から、当時の文化的情況が語られています。小川三四郎は、熊本から上京、先輩・同輩や「新しい女」を通して明治の東京に好奇の眼を輝かせていました。この2作品を中心に、20世紀初頭の青春像を考えてみたいと思います。 |
平成18年11月28日(火)
午後6時から7時30分 |
県立博物館 平川 南 館長
「古印(ハンコ)から日本の歴史を読む」
※終了しました。 |
我が国においては、“ハンコ”は古代国家の象徴として8世紀にはじめて鋳造されました。公印は天皇印から国印まで大きさが厳格に定められました。その役割はほぼ10世紀で終えました。その後、江戸時代後期に国学の隆盛とともに、“大和古印”と称して古代印を模した印が数多く作られました。
近年、全国各地の遺跡から出土する印、古代の文書に捺された印影、各地の神社などに伝えられる印などを総合的に検討することにより、権威の象徴としての印が日本の歴史の一断面を如実にものがたる重要な資料であることが明らかになりました。 |