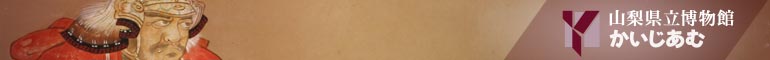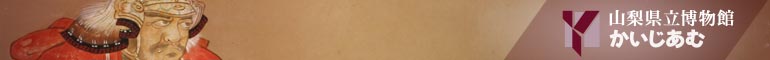◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
山梨県立博物館
かいじあむティーチャーズクラブ
メールマガジン 第11号 2007.2.6.
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
■も く じ■
1. 【クラブ事務局からのお知らせ】
・クラブ会員のご意見
・博物館は引き出しのたくさんあるタンス?!
2. 【近頃のかいじあむ】
・オオカミ展,始まる
3. 【イベント等の案内】
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
1. 【クラブ事務局からのお知らせ】
■かいじあむティーチャーズクラブ第3回研究会を2月15日(木)午後3時30分から博物館の生涯学習室で行います。あらかじめお願いした6名の先生に実践報告をしていただき,意見交換をします。また,今年度の活用事例のまとめ方について提案させていただきます。1校からお2人以上でおいでになる場合,申し訳ありませんが,乗り合わせでおいで下さい。
さて,その出欠票にコメントを書いてくださった先生がいらっしゃいますので,ご紹介して,皆さんで意見を共有したいと思います。
・各単元の内容に博物館の活用を位置づけて,その都度見学ができればいいが,バスの費用の捻出という課題がある。
・利用のしかたの工夫(体験・問題解決のためなど)が大切だと思います。
・利用者の側の要望を集めるなど,交流のしかたなども工夫できるとよいと思います。
・興味深い企画など,博物館が県民にとって身近なものとなってきていると感じる。また,小中学生でも親しめたり,楽しんだりして学べる場になってきている。まさに生涯学習の拠点としての役割をになっていると思う。基本的に3つのサービスの充実が考えられると思う。IS(インフォメーション・サービス)様々な情報の提供,AS(エリア・サービス)学習の場の提供,PS(プログラム・サービス)プログラムの提供。これらのバランスが大切田と思います。博物館の先生方,関係者の皆様のご努力に敬意と感謝を申し上げます。
・紙芝居を各学校に配付というわけにはいかないか。
・定時制の理科という立場では利用がむずかしい。
・吉田地区から生徒自身が活用するとなると交通手段が不便である。高校生向けの資料の開発が必要。
■博物館は,引き出しが無数にあるタンスのようなものです。学校の(先生の)立場だと「博物館にはどんなものがあって,どんな利用ができるんだい? それを(メニューのようなものを)示してくれないか?」となりますが,それをやろうと思ったら,引き出しが多すぎて,たいへんです(やっていないわけではありません。それについては後日,書かせていただきます)。
一方,学校の先生方から「こんな目標で(趣旨で・内容で)見学をさせたいのだが」とか「こんなものを見せてもらいたいのだが」という具体的な(できるだけ絞り込まれた)リクエストをいただけると,こっちも「それだったら,こんなものがありますよ」「担当の学芸員に相談しますよ」と,迅速に,先生方のご希望に沿った対応をすることができます。
先日,小学校4年生の社会科見学の下見に来られた先生から「なりわいの現場に,いくつか昔の道具があるが,他の道具は見せてもらえないか?」というリクエストをいただきました。とはいえ,「昔の道具」というだけでは,まだ絞り込みが足りません。先生と一緒に考え「今(の道具)はこんなふうになったけど,昔はこうだった」という違いが分かりやすい(メリハリのある)資料を用意しようという方向性を決めました。
担当学芸員に相談し,子どもたちに見せてもいい(さわっても大丈夫)資料の中から,その方向性に沿ったものを探し,陶製の枕,油紙の傘,げたスケート,湯たんぽ,石板などを体験学習室に準備し,子どもたちにスケッチしてもらったり,気づいたことをメモしてもらったりしました。
博物館の活用は,ある意味,ネットの検索に似ているかもしれません。キーワードを絞り込めば絞り込むだけ,お目当ての活用法に行き当たりやすくなります。
2. 【近頃のかいじあむ】
■平成19年2月6日(火)からは,シンボル展『オオカミがいた山〜消えたニホンオオカミの謎に迫る』が始まりました。オオカミの剥製や頭骨,オオカミの骨を利用した飾り物,オオカミの御札など,オオカミの展示品がいっぱいです。なお,オオカミ担当学芸員の取材・研究の様子をブログ風にホームページで公開中です。これも興味深いと思います。のぞいてみてください。
http://www.museum.pref.yamanashi.jp/3nd_tenjiannai_02symbol_ookami.htm
3. 【イベント等の案内】
●平成19年2月10日(土)午後1時30分から2時30分
お庭で自然観察 『生き物たちの冬越し戦略』
事前申し込み不要。無料。
●平成19年2月11日(日)午前10時30分から午後4時30分
わいわいミュージアム 『消えたニホンオオカミをさがせ!』
事前申し込み不要。常設展観覧料が必要。
●平成19年2月17日(土)午後1時30分から40分間程度
学芸員によるギャラリー・トーク 『オオカミがいた山』について
事前申し込み不要。常設展観覧料が必要。
●平成19年2月25日(日)午後1時30分から3時
館長トーク 『古代人の文字の習熟度は?』
事前申し込み不要。無料。生涯学習室。
※当初18日の予定でしたが,1週間遅くなりました。お間違いなく。
●平成19年2月25日(日)午後1時30分から40分間程度
学芸員によるギャラリー・トーク 『オオカミがいた山』について
事前申し込み不要。常設展観覧料が必要。
●平成19年3月3日(土)午後1時30分から40分間程度
学芸員によるギャラリー・トーク 『オオカミがいた山』について
事前申し込み不要。常設展観覧料が必要。
●平成19年3月4日(日)午後1時30分から3時
古文書講座『武田氏関連資料を読む』
事前に申し込んでください。無料。生涯学習室。
●平成19年3月10日(土)午後1時30分から2時30分
お庭で自然観察 『春の訪れ,感じよう』
事前申し込み不要。無料。
●平成19年3月11日(日)午後2時から3時30分
オオカミ展特別講演会
ノンフィクション作家・山根一真氏『取材10年−ニホンオオカミの謎を解く』
事前申し込み不要。無料。会場は博物館隣の総合教育センター大研修室。
【編集後記】
今号のメールマガジンは植原が担当しました。
この冬はとにかく暖かいですね。ぼくがよく行く乙女高原(山梨市牧丘町)は標高1700メートルで積雪が30センチもあるのに,2月5日午前11時半の気温がなんと15度。暖かいを通り越して暑いくらい。雪景色の中,半袖でお昼を食べました。
館の庭では,いよいよ草花たちが花を付け始めました。ウメとフクジュソウの開花初認は2月4日です。フクジュソウの花は見るからにパラボラアンテナに似ているなあと思っていたら,あの形で太陽の熱を花の中心部に集めていて,花の蜜を求めてやってきた虫たちを暖めるのだそうです。つまり,虫たちを「ストーブ付きのレストラン」で誘惑しているのです。
http://www.museum.pref.yamanashi.jp/3nd_niwa_chikagoro.htm
■配信元:山梨県立博物館 企画交流課
〒406-0801 笛吹市御坂町成田1501-1
電話:055-262-1278
ファックス:055-261-2632
△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽
|